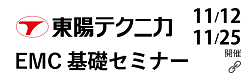検索結果
「#電池」の検索結果
HondaとGSユアサ、高容量・高出力なリチウムイオンバッテリーに関する協業に向けた基本合意を締結
2023年1月23日 HondaとGSユアサ、高容量・高出力なリチウムイオンバッテリーに関する協業に向けた基本合意を締結 本田技研工業株式会社(以下、Honda)と株式会社 GSユアサ(以下、GSユアサ)は、高容量・高出力なリチウムイオンバッテリーに関する協業に向けての...
国際規格準拠の検査でバッテリーの品質を証明 DC 耐電圧絶縁抵抗試験器 ST5680 を発売【日置電機】
2022年12月22日 国際規格準拠の検査でバッテリーの品質を証明DC 耐電圧絶縁抵抗試験器 ST5680 を発売 HIOKI(日置電機株式会社:長野県上田市、代表取締役社長:岡澤尊宏)は、バッテリーモジュール の安全検査工程に向けた DC耐電圧絶縁抵抗試験器 S...
電池の長寿命化とCO2削減のためリチウムイオン電池用導電助剤の生産能力3割アップを決定【レゾナック・ホールディングス】
2022年12月21日 電池の長寿命化とCO2削減のためリチウムイオン電池用導電助剤の生産能力3割アップを決定 昭和電工株式会社(社長:髙橋 秀仁)は、リチウムイオン電池(LIB)向け正負極用導電助剤「VGCF®(気相法炭素繊維)」の生産能力を増強することを決定しました。...
パナソニック エナジーがルシッド社の高級 EV の Lucid Air に リチウムイオン電池を供給する契約を締結
2022年12月13日 パナソニック エナジーがルシッド社の高級 EV の Lucid Air に リチウムイオン電池を供給する契約を締結 ~リチウムイオン電池のグローバルリーダーであるパナソニック エナジーが、 今後発売予定の Lucid Air Sapphire や Project Gravity SUV を含む Lucid Air のフルラ...
全固体電池の技術開発に関して大阪公立大学との共同研究を開始【GSユアサ】
2022年11月21日 全固体電池の技術開発に関して大阪公立大学との共同研究を開始 ~NEDOグリーンイノベーション基金事業「先進固体電池開発」を加速~ 株式会社 GSユアサ(社長:村尾 修、本社:京都市南区。以下、GSユアサ)は、国立研究開発法人新エネルギー・産...
中国においてEV用バッテリーをCATLから長期安定調達【本田技研工業】
2022年12月8日 中国においてEV用バッテリーをCATLから長期安定調達 ~EV「e:Nシリーズ」向けバッテリーを2030年までに123GWh調達~ Hondaの中国現地法人である本田技研工業(中国)投資有限公司(本社:北京 総経理 井上勝史)は、2022年12月8日現地時間16時(日本時...
Hyundai Motor GroupがMetaplant America EVおよびバッテリー専用工場を起工
2022年11月2日 Hyundai Motor GroupがMetaplant America EVおよびバッテリー専用工場を起工 •米国での新規設備への投資額は約55億4,000万ドル •2025年前半に生産を開始、年間生産能力は30万台 •E-モビリティソリューションのグローバルリーダーを目指す •Hyun...
トタルエナジーズとヴァレオ、EVのバッテリー冷却のイノベーションと、CO2排出量の削減に向けて提携
2022年10月24日 トタルエナジーズとヴァレオ、EVのバッテリー冷却のイノベーションと、CO2排出量の削減に向けて提携 2022年10月20日パリ発表) トタルエナジーズとヴァレオは、非常に高性能な、新しい誘電性流体を使用して、電気自動車(EV)のバッテリーを冷却する革新...
火災事故につながる潜在不良バッテリーの流出を防止 絶縁抵抗試験器BT5525 を発売【日置電機】
2022年10月24日 火災事故につながる潜在不良バッテリーの流出を防止 絶縁抵抗試験器BT5525 を発売 絶縁抵抗試験器BT5525 HIOKI(日置電機株式会社:長野県上田市、代表取締役社長:岡澤尊宏)は、バッテリー生産ライン向けの 絶縁抵抗試験器BT...
CATLとダイハツ、戦略的協力に関するMOUを合意
2022年11月11日 CATLとダイハツ、戦略的協力に関するMOUを合意 Contemporary Amperex Technology Co., Limited (以下CATL) とダイハツ工業株式会社 (以下ダイハツ) は、日本でのeモビリティを促進するためのバッテリー供給とバッテリー技術に関する戦略的協力のMOUを合意し...